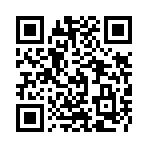2019年02月04日
古事記再読 その2

2019.2.2 チャイコフスキー・ピアノ協奏曲第一番 YouTubeからゲット 以前紹介した女性ピアニストです
渡部さんの古事記再読 その2だ。
7章 須佐之男命(日本書紀からの引用多)ーー 樹木を作った、和歌の三十一文字の始まり、出雲での幸せな結婚(八岐大蛇を退治した男と両親に可愛がられた女の結婚)ーー 行事があれば植樹祭はつきものだし、結婚後出雲に新婚旅行(神話の理想の結婚にあやかりたい?)は多かったでしょう。身分の区別のない和歌の始まりがここで生まれたのも面白い。
8章 神武天皇の建国神話ーー 「神代」と「人の世」を分けるもの(女・天照大神から男・神武天皇、九州から大和、戦いの始まり)、日本独特の建国神話と言霊信仰を受け入れる風土 ーー 一方、神話のない国の戦い(同胞の殺戮 白人の残酷な植民地政策)ーーロシア革命とかドイツのユダヤ民族扱いとか文化大革命など大きな争いごとは多い
9章 仏教伝来ーー 用明天皇が仏教を受け入れたが、神道(伊勢神宮参拝)は残る。ーー 鎮守の森の社と菩提寺の共存、家庭では神棚と仏壇。ーー 神道の日本以外は考えにくい。
10章 日本武尊の武勇伝ーー 武勇伝のため、ほとんど歴史教育で無視されている神、熊襲征伐において武勇のみでなく頭脳を使った点、「武士に二言はない」という言葉はいろんなケースを考えた対応策が大事であり、手抜かりのために失敗したとしても弁解できない。これは現代の外交においても良い教訓となる。
11章 日本武尊への愛情表現ーー 火攻めにあった時に気遣ってくれた日本武尊を思い海の怒りを鎮めるために入水した妻の存在、戦争に行く夫や恋人を見送るかつての女性たちの気持ち、これらの愛情表現が男女差別撤廃とか、武器の高度化で男らしさ・女らしさが消えてしまった。ー いいことなのか、どうなのか。要は明らかに男と女の関係が違ってきた。自己犠牲愛、瀬戸際の愛、これらが薄れている。
12章 女神・天照大神が日本民族文化の継承者ーー 日本が外国のものでうけいれなかったものがいくつかある、その一つが禁酒法、神事に酒は不可欠ゆえ無理、アメリカと日本の主婦の違い、日本の主婦は子供の養育を担当しかつ、お金の実権も握っている。一方、アメリカでは夫のパートナーが前面にあり、子育ては二の次で家庭での居場所がない、この結果としてウーマンリブ 働きに出る。大もとの伊勢神宮は女神の天照大神が主神。ー 日本では女性は前面・表に出ている。こんな日本でウーマンリブの意味は?
自分なりのまとめゆえ、なんだこれはという内容になってしまった。
戦前の教育は古事記の延長と言える17条憲法とか、帝国憲法とか、教育勅語などの昔の教訓などが継承されてきたが、戦後はGHQの指示や左の方の考えで、ほとんどが飛んでしまった。主としてアメリカからのいろんな考えの輸入品がいいという発想になってきていた。
でもよくよく考えると、日本の方が歴史が古く、かつ、神話ベースとはいえ、神道がいまも生きている。
特に伊勢神宮の天照大神についてはほとんどの人が神頼みという時に頼る神だ。なぜそうなのかをたまには振り返るのもいいのではないか。
後半の6章から12章のいくつかの教訓も2000年以上通用してきたわけだから、こじつけだと言わず、日本人の本来の考えという視点で素直に見るのもいいかなと思える。
古事記をどう読むか、の視点からみると、自分の変化にびっくりする。最初に呼んだときは例えば、須佐之男命が酒で酔わせて大蛇を退治する場面ではああー単なる神話だねと思う。でも、わざわざ退治に出向くとか、お酒で仕留めるとか、を考えると須佐之男命の男っぷりとか智慧を出すとか、正に教育勅語にでてきそうな教訓を含んだ神話と思えてくる。