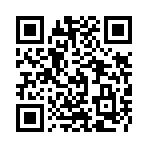2018年03月07日
登山靴の手入れ

2018.3.4 寒風より大谷山(二つ目のコブ)へ
先日の大谷山で登山靴(冬靴は革製品)の中まで濡れてしまった。暖かい日ゆえ雪が溶けていたことも要因の一つです。
もう一つの要因はコバのミシン目部分の目止め不良。これは革靴独特のもので靴底と本体を結ぶミシン目部分から水が侵入するということ。
このミシン目のことは知っていて、適当な接着剤(恐らくゴム系統)を塗っていたが、メンテがいい加減ゆえ接着剤落ちの部分が多いということでしょう。
今回は反省してわざわざネットで調べ、エキストン防水シーム材リキシームを知り、早速購入し昨日そのリキシームで靴の手入れをしていました。不慣れゆえ悲惨な状況ですがもう一回の塗布がいるようです。乾いてから再度チャレンジします。
この革靴は恐らく20年くらい(覚えていない)は使っているでしょう。靴底張替え実績は1回。ここ10年は冬場しか使っていません。4−5万したと思います。張替えは1万くらいだったでしょう。
さて、冬以外の靴はさらに3足持っています。沢靴と通常靴2足です。2足のうちの1足(1.5万くらい)は廃棄寸前のもので山以外のウオーキングで使っています。廃棄寸前ゆえ、防水は効かず裏底はすり減っているということ。山では使い物にならないので去年から幾分上等品(防水対応、2万弱)を買って冬以外はそれを使っています。寿命は1年強です。
まず底の踵部分がすり減ってきます。下りで危険なので適当に買い換えます。このすり減った靴をケチってウオーキング用に使っているということです。
現在のお金の使い道は「靴も含めた山の消耗品と山の交通費と帰りの反省会費用」、その他で「雑誌と本」と「プリンターのインク代」くらいと言い切っていいでしょう。健全財政と思うがどうかな。