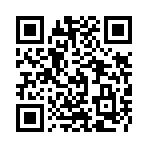2018年12月04日
京都北山ー廃村八丁 その2

2018.12.2 オリ谷から衣懸坂への道
右のオリ谷から左の衣懸坂へのコースでAが25000地図上の道、Bがヤマレコで入手した空色の軌跡、Cが我々の赤の軌跡、Dが谷、Eが尾根芯。
通常はAは当てにならず、Bが大いに参考(尾根に道ありと判断)になる。従って、Eの尾根芯ルートをまずは狙う。踏み跡はなくしかも急坂ゆえに躊躇うが赤いテープらしきものもあるので強引に登る。ここで踏み跡と出会う。その踏み跡は一方は尾根芯、一方は谷に向かっている。
従って、踏み跡を正解とすればまずDの谷を登り右手に尾根への登り口(ジグザグで尾根芯に行く)を見つけることができたはずであった。
これは結果論であり、いきなりこの正解ルートを見つけることができたら、道作りのプロでしょう。
Bの軌跡のひとは一旦谷に進んでいるので知っていたのかもしれません。ということは、忠実にBをトレースしていたらジグザグのスタート地点にであったかもしれません。ほとんどの人は強引に登って踏み跡を見つけ喜ぶと思う。
このあたりの考察が下山後のGPS解析の楽しさです。もっともこの解析が今後に生かされないのが私らしい。


2018.12.2 P847からソトバ峠への道
上から下に向かうコースで、①が25000にある屈曲点、②がヤマレコで入手した空色軌跡、③が我々の赤の軌跡。
先の説明とおり、空色の軌跡に従い進むが、ソトバ峠は隣の尾根の南にある。空色の軌跡は谷に下りて尾根に登り返している。ということで、我々は少し戻って谷にあまり下りないようにして隣の尾根(踏み跡あり)に移動した。25000の屈曲点に注意すれば踏み跡は見つかったかもしれないが、そのポイントのチェックはGPSに組み込んでいなかった。
なお、右の黒の破線は林道であり、林道経由でも目的地に行けたがわざわざ稜線ルートで歩いていた。
このケースの場合は反省点はある。①のコースがいいとわかっていながら②の軌跡で行ける(踏み跡ありかも)と踏んで①の屈曲点を無視してきた点。事前のチェックが大甘ということ。
軌跡さえ組み込んだら行けるという安易な考えと25000のルートはあくまで参考扱いことが今回の妨げとなった。
これらの出来事は時間と体力さえあれば全く問題のないことだが、例えば、倒木などで時間を要して暗くなった場合などは、このあたりの手抜き事前検討はへたすると文字通り命取りになる。
山に興味のない人にとってはつまらない内容です。山に行く者にとってはルートファインディングの技術が大事で、この程度によって工程の時間は大いに異なる。但し、はっきりとした登山道があるときは、標識のない分岐でどちらに進むかという判断で発揮される。いずれの場合もミスすれば遭難もありうる