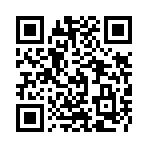2019年06月08日
日本書紀を読む

2019.6.1 峰床山ーヤマボウシ
日本書紀を読むとしたが、実際は宇治谷 孟さんの全現代語訳を読んでいるだけ。
上下2冊の中古本を入手した。先日紹介した「日本の誕生」の神武天皇の東征についての勉強から開始です。
神代は後日改めてということで、神武天皇の項から読んでいる。
古事記との対比もあるので、表のソフト(エクセル相当のMAC版)で時系列的に対比しながら、古事記と日本書紀を同時に読んでいる。
いずれも作者の記憶ベースの書物ゆえ、食い違って当たり前とは思っている。個人的にはどのくらいに違うのかなくらいの程度の興味だ。
古事記(竹田恒泰著 現代語古事記)で40P、日本書紀で20Pくらいのもの。まだスタートした直後だが、早速感想はある。
古事記と日本書紀で幾分かの食い違いはあるものの、骨子は同じ。単なる記憶の相違の類。作り話にしては骨子が同じは不自然ゆえ、やはり事実と考えた方が納得できる。
神武天皇不在論の根拠の一つは年齢に対する疑問でしょう。先に紹介した「日本の誕生」の長浜説で説明できるので、これから面白くなるでしょう。但し、天皇誕生後2600年という類の文言は見直すことになるゆえ、相当揉めるでしょう。長浜説では2019+70ゆえ概ね2090年と500年くらい短くなってしまう。
先日たまたまテレビを観ていたら(ぶらぶら美術・博物館)、朝鮮半島から焼き物技術を取得という説明があったように聞こえた。日本では縄文時代の土偶、弥生時代の土器、古墳時代の埴輪などすでに焼き物はあったと思うが?? 何が違うのかな。焼き物技術がいくつもあるということか?
再度紹介 Y染色体とミトコンドリアDNAから日本人のルーツをみる
「世界史とつなげて学べ 超日本史」 茂木誠著 KADOKAWA
「日本の誕生 皇室と日本人のルーツ」 長浜 浩明著 ワック