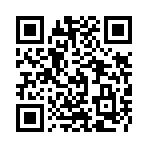2018年06月27日
決定版・日本史 その2

2018.6.25 比良・ショウキラン
先日の記事の続きです。近世;信長から江戸、近代;明治維新から第二次大戦
近世 骨子と感想 その1; 信長の比叡山焼きうち・宗教の権威無視、軍事で天才的能力発揮、部下の扱いに問題、本能寺の変、秀吉の皇室尊重・天下統一、画期的な太閤検地(尺貫法、度量衡)、無理な朝鮮出兵、家康と「貞観政要」「吾妻鑑」、関ヶ原の戦い、家康ー能力主義から長子相続制度、鎖国、封建制ー他藩との競争ー名物(天下の台所・大阪)ーーーー 戦国時代の下克上や群雄割拠は人間のレベルをアップ、信長、秀吉、家康はそれぞれの時代を担う力量を持つ。家康の長子相続による封建制の確立、鎖国が日本各地の名物を生み、安定政権が続く。家康は読んだ本の影響で「政策をもてる強み」がありそう。
近世 骨子と感想 その2; 世界に誇れる都市・江戸、豊かな時代と緊縮時代が相互に、黒船来航で「公議輿論」ー幕府の権威失墜、朝廷復活ー尊王攘夷、「日本外史」「日本政記」ー天皇復活ー維新志士の必読書、安政の大獄、桜田門外の変、大政奉還ーーーー 上水道と治安が特徴の江戸、町民・庶民の文化の開花、黒船来航で意見を聞くという権威ダウンの行動が朝廷の意見・尊王攘夷を更に誘発、桜田門外の変に続く。徳川政権は安定政権にふさわしく、江戸、大阪など世界に誇れる町を作ったが、鎖国の影響で黒船対応が弱く、これが尊王攘夷、大政奉還へのつながることになる。志士の読んだ本は「幕府の上に天皇」のスタンスだったようです。
近代 骨子と感想 その1; 公武合体論、小御所会議にて倒幕親政へ、明治維新は革命ではなく政権交代=天皇に主権が戻っただけ、五箇条のご誓文、欧米視察団の結論=富国強兵、商工重視、西郷は士農重視、西南戦争、明治憲法④(首相や内閣不在)、伝統的価値観の教育勅語ーーーー 明治憲法になかった首相や内閣不在が今後の軍部の暴走の発端なのか、伝統的価値観の集大成ともいうべき教育勅語は本当に軍国主義に連なるのかなど、その後の日本への影響。段々と今の日本のベースとなる骨格ができつつあります。 続く
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
渡部史観も半分以上は読み終えた。渡部史観は二つの特徴があると筆者が語っている。一つは皇室のあり方の変化の視点、今一つは国の体質に大きな変化の視点、変化は5回あって、6回目の変化を待っている段階。以下5回の変化点。
① 用明天皇が仏教を取り込む ② 源頼朝が宮廷と関係なく武力で鎌倉幕府を開いた ③ 承久の乱では皇位継承を幕府が管理 ④ 明治憲法(プロイセン憲法参考、一人前の国家)の発布 ⑤ 敗戦による占領憲法の制定(天皇は象徴、軍隊なし) ⑥ ??自主憲法の制定??
日本人の凄さ
「日曜美術館」とか「ぶらぶら美術・博物館」を見ていると絵や建築の分野でも世界に影響を与えていることがわかる。いろんな人が挙げられると思うが記憶にあるのは浮世絵や建物、庭の世界への影響。上の記事の江戸の文化がまさに該当する。