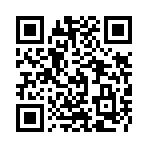2020年02月26日
自分の世界

2020.2.24 湖南・堂山の奇岩
ネットのない世界を考えてみた。
新聞、ラジオ、テレビ、講演会、いろんな会議、懇親会、お付き合い、本、雑誌などなどが情報源となる。
マスコミの実態が今と同じなら、「新しい」情報源は講演会、いろいろな会議、懇親会などのお付き合い、出版物になる。
ラジオや講演会の情報は幾分フリーのようにも思えるが、ラジオでは沖縄の我那覇さんの番組が中止となっているとか、講演会では百田さんの大学での講演が中止とかの事例もあるので結構な制約があると見ていい。出版物が活躍していたのだろうか。
とすれば、異端の考え(一般的でない考え)が世間に浸透する程度は微々たるものと言える。昭和40年くらいまではそういう世の中だったということ。
ネットのない時代に「自虐教育」が大いに普及したわけだ。田舎にいる頃は受験生はA新聞の愛読が必須だった。この延長に本多勝*の本があった。今から思えば自虐本の典型的な見本だったが、わざわざ揃えて読んでいた。彼は内容のいい加減さはすでに告白しているので本当に無駄な(金銭的にも考えの面でも)買い物をしたことになる。
この時代に自虐教育を見破って、雑誌とか本を出版されていた人がいると思うと、彼らの努力がネット社会で漸く表に出てきて感慨深いものがあるのではと思う。
ネット社会は自由かと言えばそうではない。自分で全てを手配できればそうではないが、他人の力を借りようとすればやはり制約条件が出てくる。典型的にはYouTubeでの制約。でもお金さえあればネットも買えるので自由にできそう。
これからがタイトルの「自分の世界」。従来の情報源と異なり、選択できる点が決定的に違う。出版物でも可能だが、自費出版しない限りは出版社のフィルターを通過せねばならない。
例えば、YouTubeでのお気にいり番組が自分の世界になる。経験的には自分の考えの変化とともにお気に入りも変化していく。どう成長するか、そうでないかはご本人の意図次第で決まるでしょう。はっきり言えるのは、現状のマスコミの世界では選択の範囲は狭すぎるということ。具体的にはテレビで出演を拒否されネットのみで活躍する人が現に存在する。
でも結局のところは自分の世界故、他人がどうこう言うものではない。全て自己責任での自己判断だ。
ーーーーーーーーーーーーーー
サンケイがホテルの領収書の存在をトップ記事にしたと須田さんが報告、他のマスコミは一切無視しているらしい。残念ながら不勉強故、領収書の存在の重要性がわからない。わかる人はわかるのでしょう。