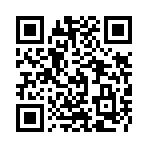2019年06月11日
カキノハグサを求めて

2019.6.10 比叡山ーカキノハグサ
昨日は雨、通常なら予定の山行は中止。
しかし行き先は比叡山ゆえ、カキノハグサのシーズンだ。
今回の山行は地元の町内の山行ゆえ、比叡山は裏山。雨が強くなれば、雷がくれば逃げて帰ればいい。
という事情で強行実施。参加者は予定の半減となるが気にしない。一人でも行くつもりだ。
問題は本当にあるかどうか、咲いていることは知り合いのFACEBOOKで確認済みだが、どこに咲いているかは聞いていない。
よって、私の知っている場所に行き現物の存在を確認するしかない。
ありました。でも確認できたのは2輪のみ。なくなれば、別の場所を探すしかない。以前より激減していると思う。
参加者は初めてゆえ大いに喜ぶ。強行実施の甲斐がありました。なければ別の場所で探し回っていたかもしれません。
2019年05月23日
写真の楽しさ

2018.5.1 蛇谷ヶ峰山麓ーキンラン
本日の山行(伊吹北尾根縦走)は不参加と決めた。
自分の運営する会の山行ゆえ、できれば参加したいところだが無理しなくていい。幸いなことには私が参加しなくても成り立つ会に成長している。喜ばしいことです。山友達に感謝。
さて、本日の話題は写真。本ブログの写真はほとんどが私の作品。但し、一部、ネットから画面を借用したものがあり、この場合は引用先は明記している。
ほとんどは山で撮った写真。時々、わざわざ写真を撮りに行くことはあるが、やはり難しい。山で歩きながら「いいな」で撮るのが私には合うようだ。
本題は作品のことではない。いつも目を楽しませてくれる場所に行ける幸せのことが主題だ。
実例が今回のように山に行けなくなっても去年の写真(風景)を持ってこれることの幸せ(去年はそういう場所に行っていたということ)をつくづく思う。
そういう感度を持っていることが幸せと思う。写真を撮らない人はその場で感激して恐らく脳裏には残っているのでしょう。私のようにすっかり忘れる人間には写真が最適の記憶マシンだ。今回も含め、去年の写真を数枚の写真を紹介させてもらったが、写真を見てその時の状況を思い出すくらいに振り返ることができる。
鼻風邪もほとんどなくなり、体のだるさのみ継続している。そろそろ、ゆるい山行にトライしてみましょう。
2019年05月10日
植物同定の難しさ


左がヤマウルシ 右がヤマハゼと思う。
理由; 側脈の数は明らかに右の写真が多い、左の写真はまだ若葉ゆえわかりにくいが、左の方の葉が丸っぽい、右の葉は成長して大きくなりそう ---------- 以上、わたしの素人判定
(できれば引用した資料をみてください。側脈と丸い葉などのきれいな写真があります)
昨日の話題で少し触れたヤマハゼとヤマウルシの相違点につき、文に誤りがあり相違点の説明部分を早速削除した。
HP掲載用の写真の説明のため整理してみると、記憶に残る相違点の内容と撮った写真を比べると、どう見ても合わない。
結局ネットで調べてみた。面白いことに記事により記載内容は一部は同じだが、違う部分もある。
要は人によって、注目しているところが違うということでしょう。
まず、はっきりしたいのは、現場で聞いた話について。
聞き手は全てを聞いているわけではない。自分に理解できることのみを覚えている。
特に理解できない単語(例えば側脈につき説明があったとしても知らない単語ーネットで知った単語)は頭に残るはずがない。
今回のケースでは葉の周りがギザギザのものがヤマウルシであり、ギザギザのないものがヤマハゼとのみ記憶してきた。
ところが、このギザギザは幼木に当てはまるようであり、成木では違うことが調べてわかった。
恐らく説明者は幼木と言っているのに、聞く側は全く聞き流している。
今、手元に3種の資料がある。
A「樹木見分けるポイント図鑑」ー林弥栄・総監修ー講談社 ヤマウルシ ハゼノキ ヤマハゼ
B 葉と枝による樹木検索図鑑 ハゼノキ ヤマハゼ ウルシ ヤマウルシ
C ウルシ属植物の区別点 ツタウルシ ヌルデ ヤマウルシ ハゼノキ ヤマハゼ
それぞれ、恐らく権威のある資料だと思われるが、
私がこれはいいと思ったのが、側脈の数(ヤマウルシは10対くらい、ヤマハゼは20対と多い)と小葉のつき方(ヤマウルシは下部(主枝)にいくほど小さく丸みを帯びる)の二つ。Bの資料がわかりやすかった。後の違いは私には理解困難。
写真は事前知識ゼロで撮っているので、撮るポイントもわかっていない写真ゆえ、ご容赦。他人の写真を利用したいが著作権もからむので遠慮しています。
2019年05月09日
春の山野草

2019.4.7 鏡山山麓ーヘビノボラズ
鏡山は384mの低山だが、山麓の谷には多くの花が咲いている。
きのうの写真はハルリンドウという山に行くひとならほとんどの人が知っている花、きょうは写真のヘビノボラズという花。
トゲがあり、確かに蛇は登りづらいだろうなと思う。
覚えている花は食中植物のイシモチソウ、モウセンゴケや黄色いニガナ、樹木の花ではアオダモの白い花、ズミなど。
昆虫ではイトトンボ。花ではないがヤマハゼとヤマウルシの違いも教わったがいつまで覚えているか。去年はヤマウルシにかぶれてしまったという苦い経験がある。
ーーーーーーーーーーーーーーー
さて、昨日は今年2回目の大和三山。15Kmというロングコースだ。大いに疲れる。
しかも、朝はガラガラ声ゆえできれば中止にしたいところだが、受付は完了し、実施ということで合意されているのでよほどのことがないと中止宣言は無理。
帰宅時点でも明らかに喉に異常があるので、来週月曜の山行に備え、再び静養です。
2019年04月17日
海津大崎の桜(ひとり車旅)

2019.4.16 海津大崎から竹生島
昨日、海津大崎の桜を見に行った。調べてみると6年振りでした。
散り初めだが、散ってはおらず持ち堪えている様子。車を途中で止めて2Hr弱の桜鑑賞ウオーキング。
写真を撮っていると、桜と船、桜と岩、桜と竹生島の組み合わせがいいなと気づく。
適当に車も人も多い。
海津大崎を終えて、奥琵琶湖パークウェイに行く。ここも数千本の桜ゆえ見応えはある。
山頂から木之本には行けず、ピストンとなる。帰りに菅浦に立ち寄る。
ここは菅浦の朝日山ハイキングの基地でもある。
多くの写真を撮って帰宅した。
やはり海津大崎と奥琵琶湖パークウェイの桜は見応えがある。しかも、適当(距離・時間・場所)にウオーキングを盛り込めるので健康的だ
2019年04月05日
桜で思うこと

2019.4.3 仁和寺の桜
梅と桜の違い、桜は汚い花びらになる前に散ってしまう。
以前にもどこかで記載した記憶があるが、桜の素晴らしさはつぼみから散るまでいつでも鑑賞に堪えることではないか。
梅は枯れてくると、さすが見るに耐えない。桜は散っている時も絵になる。しかも桜の絨毯も絵になる。
今年は桜に恵まれているように思える。3/31に伏見桃山ウオーク、4/3に仁和寺周辺のウオーク、本日4/5(金)は阪南市・山中渓(ヤマナカダニ)、明日4/6(土)は琵琶湖疏水。明日までの晴れ予報は確定。
4/8(月)はタイミングが合えば(天候と桜の様子)、哲学の道近辺をうろうろできるかも。さすが4/10(水)の米原・彦根は遅いだろう。
いずれもハイキング関連の行事だが、この季節に相応しく、ウオーキングも適当に組み込んである。
昨日のテレビで京都植物園の紹介していた。良さそうだが、今年は行くことは無理でしょう。4/3に通った原谷苑の桜も見たいところだが、これも無理だろう。御室桜は見れる機会がありそうだが、私好みの桜ではなさそうな様子だ。
さて、個人的にここはいいと思っている場所はどこかと問われたら、優劣等の比較はなしとして、背割堤(三川合流)、海津大崎(琵琶湖)、琵琶湖疏水沿い、哲学の道、お寺や神社の桜などでしょうか。
結局のところ、桜だけではダメで何かが欲しい。雰囲気が欲しい。建物か設備か、湖か川か。どこの桜かわかる方がいいかなと勝手に思う。2−3年前、東京の公園の桜を見に行った。高層ビルと桜の組み合わせも本当に良かった。背景が大事と信じている。今年はどんな背景を組み込めるのだろうか。
2019年03月14日
猪名川ウオーク

2019.3.13 伊丹空港・離陸直後
昨日はJRを利用する人にとってはトンデモナイ日でした。その一人が私。
山のグループで猪名川ウオークの企画(伊丹ー北伊丹)があり、前日(一昨日)に参加表明。
比叡山坂本で1Hr遅れの列車に乗る。ところがなかなか京都に着かない。リーダー宛て、集合時間までに行けないので「一人ぶらぶらウオーク」に切り替えると連絡。
結局、概ね1.5Hrで着けるはずのところ倍の3Hrで着く。(一人歩きと決めていたので、グループとは逆コース(北伊丹ー伊丹))
逆コースの意図は伊丹空港の見えるスカイパークでゆっくり写真を撮りたかったため。
1Hr遅れで北伊丹を出発。下河原緑地で飛行機のお腹を見せてもらう。が、この時点ではここが貴重な場所の認識はなし。
猪名川沿いに南下し、桑津橋から東の空港に向かう。途中のコンビニで昼食を購入し西桑津公園で昼食。
伊丹スカイパークに着く。概ね2Kmくらいなのでしょう。滑走路沿いに公園が続く。発着の都度写真を撮り楽しむ。
上の写真はその1枚、大した写真ではないが、どこで撮っていいかもわからない状態での写真ゆえ、よしとしましょう。
さすが、三脚利用のカメラマンは10人以上はいた。私はフェンスとか利用して手ブレ防止をしたつもり。
結局は腹の見えるところから出発地点、着陸地点まで、存分に見たことになる。
田能遺跡も見てJR伊丹駅に向かった。
飛行機に乗ったことはあるが、写真に撮ろうとしたのは今回含め2回くらいでしょう。
家で写真をチェックしてみると、意外にブレもなく撮れてるなと自己満足する。ただし、機体の位置はさすが無茶苦茶だ。ファインダーではなく液晶ゆえ仕方ないです。
今回をいい機会として三脚持参で朝から写真もいいなと本当に思う。やはり腹を撮りたいと思う。
やはり初心者だ。腹の撮れるところでは1枚も撮っていない。スカイパークに行って初めて腹の撮れるところの価値に気付く。
2019年03月09日
しだれ梅三昧

2019.3.8 鈴鹿の森の梅
先日知人からTELがあり興奮した口調で「鈴鹿の森のしだれ梅はすごいに尽きる。ぜひ行ってくれ。」 ということで、昨日の晴れ間を利用し家内と二人で出かける。
イメージとしては福島にある花見山を頭に描いてた。ここは春の樹木の花が満載の低い山。
鈴鹿の森という名称からして山麓の空間の利用かなとと思ってHPを覗くとアクセスの案内からしてあれれ、これは平地にあるな、イメージが違うなと思う。やはり、「鈴鹿の森庭園」という名が相応しいでしょう。
さて、場所は鈴鹿ICから5−10分の距離でありすごく便利。入園料は1500円、高いと思うか安いと思うかは各々の判断。私はせっかくゆえ、梅の本数はこれでよしとしても、倍くらいの広さで散歩を兼ねるくらいならいいなーと思えた。
入るとやはりすごいの一言に尽きる。狭いというほどではない庭園に名木が数十本。加えて、河津桜のような早咲き桜が数本。
一本一本が大きな樹木ゆえ、見応えはあると思う。一度訪問されたらどうでしょうか。
帰宅後、パンフを見ると研究栽培農園とのこと。なるほどそうだったのかと納得した。
2019年03月08日
観光地の案内板

2019.3.6 大覚寺ー放生池(大沢池の西)
昨日の記事の続き
嵐山ウオークの時に入手した資料(案内役のリーダーから入手)とか、帰宅後HPやブログを作成している時に見たHPの内容などから改めていろんなことがわかった。
まず第一に言えることは、各観光地(例えば清涼寺)のHPのみでは必要な情報が得られず、個人がアップしているブログやHPはものすごく参考になるということ。
各観光地にすれば、大雑把にわかってもらえればいいということなのか、単なる手抜きなのか、ガイドさんに依存したいのか、この辺りは?だが、非常にHPが貧弱ということ。
具体的に言えば、清涼寺(嵯峨釈迦堂)にある「生の六道」につき、清涼寺のHPでは説明なしゆえ、わざわざネットで調べる必要がある。せめて現地で案内板などおけば、幾分関心を持ってもらえそう。
私のような無関心・無知な人間は、これまで10回くらいきているが、「生の六道」に目が止まったのは初めてかもしれない。それも現場で説明も受けて、理解できないから帰宅後調べてやっとわかったというお粗末さ。
読む読まないは勝手として、せめて説明の標識が欲しい。この標識で、例えば入り口側のお寺に足を運ぶかもしれない。
というところが、今回のウオーキングをまとめて感じたこと。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
いかにも観光地が手抜きと非難しているように見えるが、当方のお粗末さも相当なもので
小倉山ー小倉山荘ー亀山公園ー百人一首ー藤原定家、嵯峨天皇ー大覚寺ー嵯峨院ー嵯峨天皇陵 の関連がわかったのは今回です。
ある域(レベル)に行かないと関心が向かないという典型的な事例でしょう。単なるハイキングの通過点から歴史への関心度アップということか。
2019年03月07日
嵐山周辺ウオーキング

2019.3.6 嵯峨釈迦堂の河津桜
山のグループの嵐山ウオークに参加する。企画上(降水確率からして)では雨天中止だが、皆さんと会いたいのか、暇なのか、なぜか集まる。
案内役はプロの「ガイドのできるタクシー運ちゃん」兼「山のグループのボス」
コースは大覚寺ー釈迦堂ー落柿舎ー小倉山ー亀山公園(昼食)ー法輪寺ー嵐山公園(懇親会) その他名前が出てこない隠れた観光地。
隠れた観光地はもちろん、大沢池奥周辺や法輪寺は初めてゆえ、大いに楽しむ。大沢池の「名古曽の滝跡」は正直なんでもないところだが、やはり歴史の重みでしょう。法輪寺の高台からの桜は見応えがあるとのこと。
特に今は梅の季節であり、また釈迦堂の河津桜も満開ゆえ、カメラは大忙し。
亀山公園の赤いマンサクも関西の人間にとってはびっくりもの。
嵐山公園で有志による懇親会となる。用事のある人、酔ってしまった人が一人づつ帰り、残りは暇人。
血液型、山のグループの今後などをネタにしながら手持ちのお酒がなくなるまで団欒する。
今の山のグループを存続させたいと思いは皆さん一緒であることを確認しただけでもいい日だったのではないでしょうか。
ーーーーーーーーーーーーーーー
京都の観光地はやはり歴史を知らないと興味も楽しさも半減すると思う。
残念ながら私は歴史は本当に初心者ゆえ、ガイドの説明も10%くらいの理解度。
今後の課題として残しておきましょう。
知人から、竹田から歩いていける城南宮の梅と鈴鹿ICからすぐの「鈴鹿の森」の梅を見るべきという助言をもらう、
一箇所くらいはいけるでしょう。