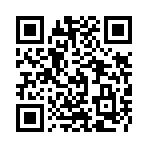2019年07月15日
「奇跡の経済教室」を読んで

2019.7.13 「奇跡の経済教室 P135」 財政支出の伸び率とGDP成長率
先日紹介した「奇跡の経済教室」(中野剛志著 ベストセラーズ)の前半を読み終えた。後半は著者と反する見解を持つ学者への批判集です。
消費税増税は日本を滅ぼすなどの類の本は読んできたので、消費税増税反対については異論はないが、基礎的な部分がわかっていないので、強引に納得したという面がないではない。今回読んだ本は基礎の基礎の本だが、それでも100%理解したわけではない。でも以前より明らかに消費税アップの弊害は理解できたと思う。
経済学の理論が絡んでいるように思うが、素人ゆえに何が理論かは?。でもはっきり言えることは、消費税アップ論者たちの予言通りには世の中が動いていないのに依然として増税を主張続けるという理解不能の行動をとっている学者たちが堂々と日本で存在できるというのは不思議なことだ。歴史学者同様、どこかの大学が学者たちをコントロールしているのでしょう。
ここで要約を書くことは困難ゆえ、本を読んで、まさに「目からうろこ」という部分を取り上げて、いかにすればデフレが脱却できるかを示したいと思う。
本のストーリーに従って、箇条書きで整理する。
1 過去20年間の経済成長率の推移(藤井さんのグラフそのものを引用)ーー 日本のみマイナス成長で最下位(80カ国くらい)、経済破綻したギリシャでも+40%
2 デフレが20年続いている。ーー 貨幣の価値が上がっている(ものを買わず作らず、お金を貯める)、民間ではなく政府の政策が悪い
3 政府はデフレ下でインフレ対応策を実施 ーー 財政支出の削減、消費増税、行政改革、規制緩和、自由化、民営化(増税以外は聞こえのいい政策)ーー 倒産は増え、解雇などが進む、自然淘汰など聞こえのいいことをいう
4 銀行は預金通貨という通貨を創造する。ーー 銀行預金がなくても貸付という名で通貨を発行できる,貨幣の80%はこれーー 目からうろこです(なぜ銀行は預金を集めるかは説明あり、大事なことは預金あっての貸付ではない、借り手があれば貸付できるということ)
5 デフレの時、日本銀行は各銀行の準備預金を増やせるが、借り手に資金需要がない限り、銀行の貸し出し(通貨の創出)はないーー 教科書には日本銀行が貨幣供給量を操作できると記載(インフレの時は正しい)、借り手があっての貸付。
6 最も大事なこと、国債発行(財政赤字)が通貨(預金)供給量を増やすーー 一言で説明できず、信用貨幣論では貨幣は負債、よって、仕事を作って国債発行がデフレ対策となる
7 6と同じだが別の言い方、借り手の需要の増 →銀行の貸し出しの増 →貨幣供給の増 、まず仕事ありきであって、金利とか日銀の準備預金は影響なし
8 現代の貨幣は金の価値に裏打ちされた「商品貨幣」ではなく「信用貨幣」ゆえ、返済可能な限り無限に預金通貨を発行できるーー 錬金術が可能
9 財政赤字の制約(限界)はインフレ率ーー コントロール可能
10 税は財源確保ではなくインフレの行き過ぎ防止ーー 無税ならハイパーインフレとなる
これまで読んできた本では理解できなかったことが漸く理解できる。
銀行からの貸し出しが貨幣を生むとか、税金は財源確保の手段ではなくインフレ抑制とか、非常に新鮮でした。何はともあれまずは投資ー貸し出しーデフレ脱却ということでしょう。もしインフレの危険性が増したら、インフレ策を取ればいいだけ。インフレ策は聞こえがいいので容易だが、デフレ策は財政赤字など抵抗があり取りにくいだけに困難度大。