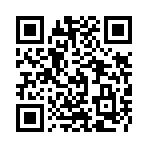2020年06月24日
読*新聞の感染症対応への提言

2020.6.22 比叡山・本坂
読売新聞が7つの提言をしている。
私が真っ先に浮かぶのが、日本単独での自活(食糧やマスク、生活必需品などの緊急物質の自給自足)だが、なぜかこの指摘はない。一体何を学んだのか。今一つが危機管理。この危機管理については提言に盛り込み済で首相直属の組織を作れという。ところが視点は感染症対応の組織しか念頭にない。
危機管理は感染症だけではない。周辺の出来事からも容易に類推できる。戦争、暴動、領土侵略、拉致、テロなど。
この二つが大事なことでしょう。国際分業とかグローバリズムなどは言葉や意味は綺麗だが、いざ、緊急事態発生時はそれでは対応できない。今回はいろんな体験をした。マスク不足、防護服不足、パン粉不足、ミシン不足などなど。要は国内でも調達できるように(100%かどうかは物によるだろう)日頃から体制を整え、余分な分は輸出というスタンス。お金は体制作り・こんなところに使う。
同じように海外の観光客(インバウンド)に依存しない内需型の観光が主体。但し、来る人拒まずのスタンス。
日本の高い野菜を海外のお金持ちのところに輸出し、海外の安い野菜を日本の一般家庭に。これはどこかおかしいのでは。日本の家庭に届ける野菜を作るのが本来の姿ではないのか。余った野菜を輸出するのは大いに結構。もし、これ(体制作り)にお金が必要ならここでもお金を使うべき。
国際的に分業するなら、それなりに対等(物々交換、要は互いに助け合うというスタンス)でなくてはならない。C国との取引は異常(利益の一方的吸い上げ)。
内需型の日本なのにこれほどの体験をした。K国の被害の大きさはこれから顕在化するでしょう。