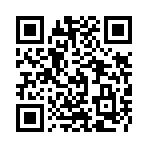2022年04月01日
琵琶湖疏水の花見

2022.3.30 伏見・宇治川支流 --南コースの最後
琵琶湖疏水の花見は数十年前に滋賀に来てから行っていたと思う。
が、残念ながら勉強不足で、「浜大津から哲学の道までくらいまで桜がいい」の認識しかなかったと思う。その後、2012年に自分が案内する立場になって、図書館の本とかネット情報(京都市水道局)などで勉強させてもらって、自分なりに説明用パンフレットも作った。
インクライン、銘板、発電、ネジリマンポ、水路閣、それらを含む国の史跡、日本の技術者の凄さ、傾斜の少なさなどなど、学んだことは多い。これだけ学んでも歩くのは「浜大津から哲学の道まで」と進歩はなかった。ーー 但し、忘れている。
去年の春、理由は忘れたが、琵琶湖疏水の踏破を目標にしたようだ。堀川通りまでの北コースと伏見までの南コースと勝手に命名し、一人で下見(疏水沿いに忠実)、桜に合わせてグループでトライアル(締めにふさわしい場所を経由して駅に)となった。一日コースという制約もあり、北コースは鴨川から植物園へのコース、南コースは伏見の桜名所を考慮し、宇治川支流へのコースに変更している。
いずれも桜満足コースゆえ大いに好評?だったと思う。そして今年もとりあえず南コースは終えた。残りは北コースだが、桜が盛んに散っている時かもしれない。私の体調と天気と他の計画との調整の結果でありやむ終えない。
長い琵琶湖疏水に沿って歩いて思うことは、琵琶湖と京都のつながりの強さだ。京都府知事の読みの凄さはさすがだ。設計担当の若き田邊朔郎さんもすごい。記憶では外国人技師がギブアップ?。
琵琶湖疏水を案内して思うには、琵琶湖疏水の意味には無関心で関心は桜のみの人もいるということだ。去年、疏水の踏破を思ったのは案外、疏水の凄さを目で確認したかったのかもしれない。最後に大津から蹴上までの勾配は約2mで1mmの傾斜のはず。
なお、メインブログは「まめじろうの活動日記」です。